家庭教育
子どもの自己肯定感や社会性の発達を促す居場所づくり
~ 互いに寄り添い、支え合える取組 ~
近年、小・中学校には発達障害の児童生徒だけでなく、学習面・行動面・コミュニケーション面など様々な面で課題があり、特別な教育ニーズのある幼児児童生徒が増えてきている。学級や学校での集団活動にうまく適応できず、自己肯定感が下がり、登校渋りや不登校につながってしまう場合もある。
一方、保護者は、様々な課題や背景ゆえに、子どもの課題を一人で抱え込み、家庭でどのように子どもに接すればよいのか悩み、孤立してしまう場合もある。
果たしてそのような中で、学校・家庭・外部機関は子どもが抱える課題に対して何ができるのだろうか。
どのような連携をすることが、未来を担う子どもの利益になるのだろうか。保護者が安心して「子育て」や「家庭教育」ができるよう、社会全体で支え合うことの大切さを会場の皆さんと一緒に考えていきます。
講 演 者

川村 修弘 氏
【プロフィール】
宮城県塩釜市生まれ。小学校3年生まで塩釜市で過ごし、その後、父の転勤により青森県青森市へ引っ越しました。以降、公立小・中学校および青森県立青森東高等学校で学び、およそ9年間を青森市で過ごしました。
大学は宮崎大学教育学部に進学し、同大学院を修了。その後、宮城県内の小学校および特別支援学校に教員として勤務し、2023年3月に退職するまで、特別支援教育コーディネーターや教育相談を中心に担当しました。担任・保護者等の支援者とともに、子どもたちの成長・発達を支えるための支援を考え、実践してきました。
現在は、山形大学大学院教育実践研究科の准教授として勤務し、学部・大学院で特別支援教育の講義を担当しています。また、山形県内の教育委員会と連携し、専門家チームの一員として学校を巡回しながら特別支援教育の推進にも関わっています。さらに、宮城県の聖和学園短期大学では非常勤講師として保育士養成にも携わっています。
現代の子どもたちは,学校や家庭だけでなく,地域の施設やクラブ活動,放課後児童クラブなど,様々な場所で過ごしています。しかし,これらの居場所には支援のばらつきがあり,質が十分とはいえません。教育現場では自己肯定感や社会性を育てる取り組みが進んでいますが,地域や家庭によっては関わりの機会が減り,SNSの影響で他者と比較しやすく,自己肯定感に悪影響を及ぼすこともあります。また,大人の支援が不足すると,子どもたちが心理的サポートを受けにくくなり,心の成長に影響を及ぼす可能性もあります。こうした課題に対応するには,地域・学校・家庭が連携し,子どもたちが安心して過ごせる居場所と支援体制を整えることが重要です。
コーディネーター

大橋 雄介 氏
【プロフィール】
NPO法人アスイク 代表理事
社会福祉法人明日育福祉会 理事長
一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク 理事
宮城県児童館放課後児童クラブ連絡協議会 理事 等
リクルートにて組織開発・人材開発のコンサルティングに携わった後、独立。NPO法人せんだい・みやぎNPOセンターにてソーシャルビジネスの立ち上げ支援プロジェクトに従事した後、2011年の震災直後にアスイクを立ち上げ、自治体をはじめとしたクロスセクターの協働により、子どもの貧困、不登校、ヤングケアラーなどの生きづらさに取り組む。著書に、「3・11被災地子ども白書」等。
こども家庭庁こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会委員、仙台市子ども子育て会議委員、宮城県子ども子育て会議委員等、多数の審議会の委員を務める。
貧困、不登校、ヤングケアラーなど、様々な生きづらさを抱える子どもたちの居場所をつくってきた立場から、本分科会のテーマである「子どもの自己肯定感や社会性の発達を促す居場所づくり」について、考えを深めるキッカケをつくることに貢献できればと考えております。

野木 和洋 氏
【プロフィール】
2015年4月 いわき市立御厩小学校PTA会長 内郷方部PTA連絡協議会会長 第13回いわき市PTA研究大会実行委員長
2020年4月 いわき市立内郷第一中学校PTA会長
2022年4月 いわき市PTA連絡協議会会長・福島県PTA連合会副会長 福島工業高等専門学校後援会会長
「頼まれ事は試され事」ということで頼まれた事は断らないことに決めているためパネリストを引き受けましたが、家庭教育のカテゴリーで何を話せるのかと問われると全くの未知数です。先日15歳未満の子どもが1400万人を割ったというニュースがありました。私自身も急激な少子化の中、普通高校・大学の存在価値が問われる時代になったと考えています。「自己肯定感」と「居場所づくり」。その場所とは果たして学校なのか?家庭なのか?

早坂 千尋 氏
【プロフィール】
平成16年度~ 仙台市立の小学校教諭として採用
平成22年度~ 仙台市立六郷小学校で,東日本大震災の大津波で被災した仙台市立東六郷小学校との統合や,黒潮太鼓の継承に携わる
令和4年度~ 仙台市立芦口小学校に勤務 現在,児童支援・いじめ対策担当・地域連携担当
令和6年度 国立教育政策研究所 社会教育主事講習修了
令和7年度~ 仙台市嘱託社会教育主事委嘱
子どもたちのより良い成長を願い,仙台市の小学校教員として勤めてきましたが,近年,様々な課題を抱える児童が増えてきていると感じております。微力ながら,一人一人に寄り添った支援を模索し,家庭・地域との連携を大事にして子どもたちとの関わりを深めてきました。子どもたちの学びを支えていくために,学校・家庭・地域に何ができるのか,皆様と色々お話することで,私自身も見つめ直したいと思います。
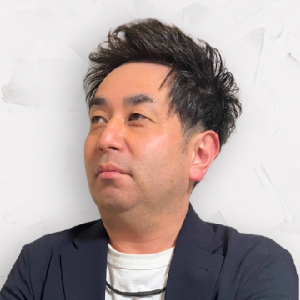
金野 貴博 氏
【プロフィール】
岩手県大船渡市在住/自営業
高校2年生の長女・中学3年生の長男・小学3年生の次男の父
《PTA役員歴》
•令和2年度~令和5年度 大船渡市立猪川小学校PTA会長
•令和4・5年度 一般社団法人岩手県PTA連合会 副会長
•令和6年度 大船渡市立猪川小学校PTA副会長/大船渡市立第一中学校PTA副会長
•令和7年度 大船渡市立猪川小学校PTA副会長/大船渡市立第一中学校PTA会長 一般社団法人岩手県PTA連合会 理事
PTA活動を通して、子どもたちの成長を見守るとともに、自分自身も多くの学びを得ることができました。
保護者も先生方も無理なく活動できるよう、役割や体制を見直しながら、規約変更に取り組みより参加しやすい仕組みづくりにも取り組んできました。
今回のパネルディスカッションでは、これまでの経験を正直に、等身大でお話ししながら、参加される皆さまのヒントになるような気づきを少しでもお届けできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

