地域連携
地域で共に育む子どもたち
~ 地元に住みながら世界とも勝負できる人間を育てる ~
少子高齢化が進むなか、私たちの地域でも若年人口が減少し、地域の担い手や子供の数も急速に減っています。これにより、地域が持っていた本来の教育力や支え合いの力も弱まりつつあります。一方で、社会全体では技術革新や価値観の変化が加速し、予測困難な時代が訪れています。こうした中で、地域や学校、家庭の大人たちは、子供たちに「どこでも、どんな状況でも生き抜く力」を本当に育てているでしょうか。都市に行かなければならない、組織に属さなければ生きられないという旧来の考え方から離れ、「地元に暮らしながら、自らの生業を築き、豊かに生きる」未来像を描く必要があるのではないでしょうか。今こそ、地域での教育の在り方を問い直す時です。
これからの教育において重要なのは、「どこに暮らしていても、世界とつながり、自分らしい生業を築き、幸せに生きられる人」を育てることです。そのためには、子供たちが自らの手で仕事をつくる力を育む教育が必要です。これはもはや学校だけ地域だけで完結する話ではなく、子供に関わる全ての大人たちの出番です。地域の資源や人とのつながりの中で、子供たちが挑戦し、失敗し、また挑戦する環境を共につくること。そして子供が芽生えさせたアイデアや意欲の芽を、大人が信じ、支え、後押しする土壌を築くこと。さらに大人自身も、子供に勇気と自信を与える日々の接し方を見直す必要があります。地域に根を張りながら、世界ともつながる人を育てるには、今、私たち大人自身の在り方が問われています。
講 演 者

泡渕 栄人 氏
【プロフィール】
1971年生。1997年旧文部省入省。2006年、「早寝早起き朝ごはん」国民運動立ち上げメンバーとして約6年企画・仕掛けを担当。子どもの生活習慣の改善に貢献。2012年、東日本大震災対応のため内閣官房宮城現地対策本部参事官、復興庁初代石巻支所長として4年余現地で復興に尽力。2016年、内閣官房「まち・ひと・しごと創生本部」から山形県長井市へ派遣。「地方に住みながら、世界と勝負できる子どもを育てる」教育方針を立案し、親子の信頼構築を基盤にした早期国語教育と、オンライン英語教育、小学生からのアントレプレナーシップ教育を推進。2019年、山形大学学術研究院教授。不登校の改善と親の関わり方に関する実践的な研究に取り組み、改善手法の手がかりを見出す。2022年、シリコンバレー発ITベンチャー企業に派遣。2024年から文科省現職。2025年4月より、内閣官房地方創生支援官を併任。現在岩手県葛巻町の伴走担当として人口減少社会の地域課題に向き合う。寄稿歴に『月刊致知』(致知出版社)「家庭教育の変革」、『内外教育』(時事通信社)「明日の教育」など。東京単身赴任中。家族は仙台市泉区在住。子ども4人。岩手県葛巻町出身。
被災地復興や地方創生での現地経験を通じて得たことは、ウェルビーイングの実現と地域の持続的活力のためには、創造的課題解決力を涵養する生活・教育環境の整備と、地域・学校間の協働体制が不可欠であることです。この、アントレプレナーシップ教育を応用し、個の力を地域での生業へと展開する仕組みづくりの重要性を経験をもとに提起します。加えて、仮想空間を活用した不登校支援の事例をあげながら、自己肯定感を基盤とする親子関係支援の実践手法も紹介。当日は、家庭や地域ですぐに実践できるよう体験いただきます。
コーディネーター

庄子 修 氏
【プロフィール】
昭和52年,宮城県の公立中学校を皮切りに,国公立の小中学校や教育行政に勤務。仙台市の教育指導課長時代には,仙台版キャリア教育の「仙台自分づくり教育」を創設するとともに,各小中学校に「地域連携担当者」を位置づけるなど,学校と地域との連携の充実・発展に尽力した。仙台市立富沢中学校長時代には,仙台市PTA協議会副会長や仙台市中学校長会長も務めた。定年退職後は,宮城教育大学特任教授として「p4c」の実践・研究に取り組んだ。
現職時代の話です。地域からの依頼を受け,河原の清掃や夏祭りの準備に取り組んだ中学生。なんとその多くがリピーターとなって別のボランティアにも参加していたのです。見知らぬ地域の大人からの「有難う」は,「魔法の言葉」だったのでした。日本の子どもの課題と言われている自己肯定感や自己有用感の醸成。その鍵は,地域・家庭との関わりの中にあるのかも知れません。

髙谷 和也 氏
【プロフィール】
令和4年度 藤崎町立藤崎小学校PTA副会長
令和5年度~ 藤崎町立藤崎小学校PTA会長
プロフィールをご覧の通り、PTA初心者マークです。どちらかというと、地域の中で子ども達と関わっ
てきたほうが長く、子ども達からは「地域の人」という印象が強いかもしれません。
実際PTA活動に携わり、子ども達の為により良い教育環境を整えてあげようと様々な活動や交流を通じて、これだけの大人が子ども達を支えているのに気付いたのと同時に、今大会に参加の皆様の熱い思いを聞いて勉強したいと思います。

眞野 美加 氏
「子どもたちの育ち」を学校と家庭で抱え込みがちな時代だからこそ、地域がもうひとつの「居場所」 「見守る目」として、私たち保護者世代も見直す時です。私は地域・家庭・学校を対等な三者とする協働を目指して活動してきました。PTAも「子どもの育ちを共に支える仲間」として再定義できる可能性があります。今日は私自身の失敗や試行錯誤も含めた実践を共有しながら、皆さ んと一緒に「地域と共に育つ」子どもたちの未来像を考えられたら嬉しいです。
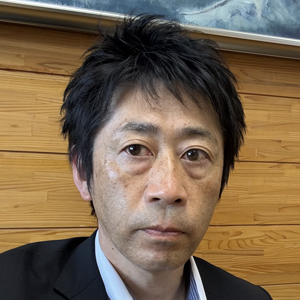
橘 範広 氏
【プロフィール】
秋田県大館市在住(羽後町出身)
宮城教育大学教育学部教育心理学コース卒業
R3~R5 大館市立釈迦内小学校教頭
R6 大館市立有浦小学校教頭
R7~ 大館市立釈迦内小学校校長
大館市では、「大館盆地を学び舎に、市民一人一人を先生に」をコンセプトに、「おおだてふるさとキャリア教育」を展開し、ふるさとを担う気概と能力を備えた「未来の大館を創造する力を備えた人材」の育成に取り組んできました。
本分科会では、おおだてふるさとキャリア教育の一環として、本校が地域と学校が協働しながら14年間取り組んできた「ひまわり活動」の足跡と、活動を通して子どもたちに培われた力、今後の展開について紹介していきます。

